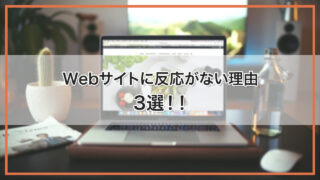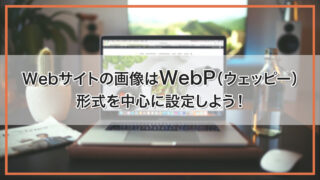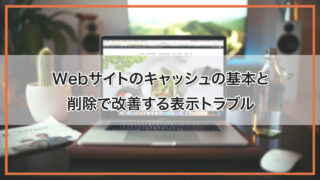Webサイト運営・制作をするなら知っておきたいSEO対策(施策)
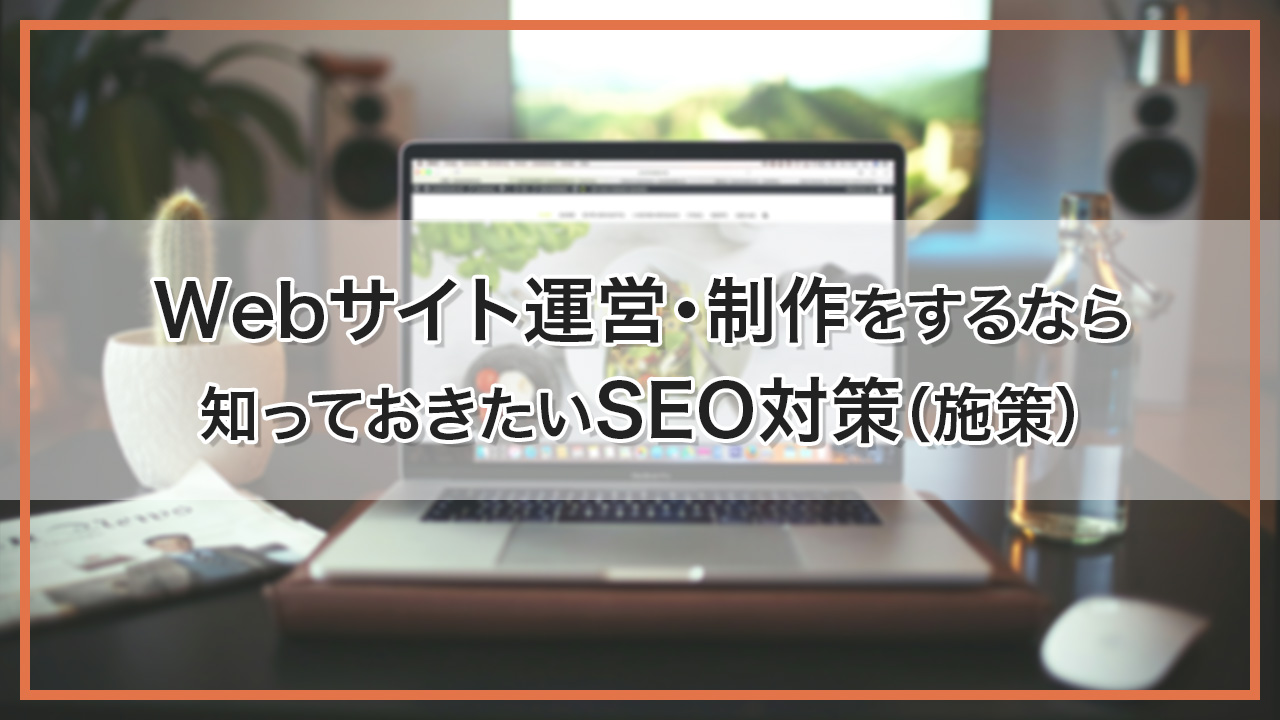
Webサイトを運営している、あるいは制作する目的のひとつはGoogleなどの検索結果で上位表示されて、見込み客にサイトを訪れてもらい、何らかのアクションをとってもらうことだと思いますが、そのために重要なようそがSEOです。
SEOとは、検索エンジン最適化の略であり、自社サイトをGoogleなどの検索結果で上位表示させるための施策全般を指しますが、「何から始めればいいのか分からない」「効果があるのか不安」と感じていませんか?
SEOの基本を理解しておけば、制作会社に依頼する際に細かい要望を伝えることができたり、どんな施策が効果があるのかを判断することができます。また、WordPressでサイトを運用しているなら、自分で対策を進めることも十分可能です。
この記事では、SEO対策の代表例とそれぞれの効果の違い、Googleのアルゴリズムとの関係、SEOが意味ないと誤解される理由などをわかりやすく解説します。また、SEO対策を自分で行う際のポイントや、継続的な改善によって成果を出すための考え方も紹介します。検索順位を上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
- SEO対策の基本的な仕組みと種類
- 自分でできるSEO施策の進め方
- SEO対策の費用感と会社の選び方
- 継続的に成果を出す改善の考え方
SEO対策(施策)の基本と押さえるべき要点

SEO対策(施策)とはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)
SEOとは、「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、Googleなどの検索エンジンで自分のWebサイトを上位表示させるための施策全般を指します。検索結果の上位に表示されることで、多くのユーザーにサイトを見つけてもらいやすくなり、アクセス数や集客効果が期待できます。
先ほどから「(施策)」と補足をつけているのには理由があります。
今ご説明した通り、SEOという言葉は「検索エンジン最適化」という意味なのですが、「SEO対策」と言うと、「検索エンジン最適化対策」となってしまい、二重の表現、あるいは最適化に対する対策(検索エンジン側が施策する対策)のような意味となってしまい、本来の意味とは異なるものになってしまいます。
しかしながら、世間一般やWebの界隈でも「SEO対策」という言葉が「SEOのために行う施策」という意味で使われることがすでに慣例となっていますので、以下の記事では「SEO対策」という言葉で解説を進めていきたいと思います。
SEOには大きく分けて「内部対策」「外部対策」「コンテンツ対策」の3つがあります。内部対策とは、サイトの構造やHTMLの最適化など技術的な面の改善を指し、外部対策は他の信頼性あるサイトから被リンクを得ることで評価を高める手法です。そしてコンテンツ対策は、ユーザーにとって有益な情報を提供し、検索ニーズに応える記事やページを作ることが目的です。
たとえば、あるユーザーが「自宅でできる筋トレ」と検索したとき、関連性が高く、信頼できる情報を持つサイトが上位に表示されます。これはGoogleの評価アルゴリズムが「検索意図に沿っている」と判断しているためです。
SEO対策の代表例と効果の違い
SEO対策にはさまざまな手法があり、主に「コンテンツSEO」「内部対策」「外部対策」の3つが代表例として知られています。それぞれの施策はアプローチも目的も異なり、得られる効果にも違いがあります。
まず、もっとも基本となるのがコンテンツSEOです。これは検索ユーザーのニーズに合った質の高い記事やページを作成し、検索結果での上位表示を狙う方法です。情報が整理されていて信頼性のあるコンテンツは、Googleからの評価が高まりやすく、アクセス数の増加や滞在時間の向上といった効果が見込めます。
次に内部対策では、HTMLタグの最適化やサイト構造の整理、ページ読み込み速度の向上などが重要になります。検索エンジンが正しくページを理解できるようにするための技術的な施策であり、特にタイトルタグや見出しタグ(h1〜h3)の使い方、画像のalt属性の設定などがポイントです。内部対策を怠ると、せっかく良質なコンテンツを作っても検索エンジンに正しく評価されないリスクがあります。
そして外部対策は、他サイトからの被リンク(バックリンク)を獲得することにより、自サイトの信頼性や権威性を高める手法です。例えば、業界メディアや大学・行政など権威あるサイトからリンクされると、Googleは「価値のあるサイト」と認識し、検索順位が上がりやすくなります。ただし、意図的に不自然なリンクを増やすと、かえってペナルティの対象になるため注意が必要です。
このように、SEO対策は単一の作業ではなく、複数の視点からバランスよく行うことで最大の効果を発揮します。どの施策にもメリットと注意点があるため、自社サイトの課題や目的に応じて優先順位を見極めながら進めていくことが重要です。
SEO対策を自分で行う手順と注意点

SEO対策は、専門会社に依頼せずに自分で取り組むことも可能です。特に小規模サイトや個人ブログなどでWordPressを使用している場合、コードを記述することができなくても自分で基本的なSEOを実施することができ、検索順位に好影響を与えることもあります。
まずは、Googleが推奨するガイドラインを理解することから始めましょう。Google検索セントラルには、SEO初心者向けに基本的な最適化のポイントがまとめられており、SEOの基本を知るには最適です。
特に重要で、取り組みやすいものとしては以下のものがあります。
- ページタイトル(titleタグ)の最適化:検索結果として表示させたいキーワードを含み、ページの内容を端的に表す30文字程度のタイトルにする。
- 見出しタグ(h1〜h3)の適切な使用:h1はページ内に1つだけ配置する。その配下にh2、さらにその配下にh3というように、階層構造をはっきりとさせる。
- 画像の最適化:必要以上に大きなサイズの画像は適切なサイズに縮小・圧縮をする。圧縮率の高いWebPやAVIFといった保存形式を用いる。
次に取り組むべきは、ユーザーの検索意図に合ったコンテンツの作成です。ただキーワードを詰め込むのではなく、読者が知りたい情報をわかりやすく、かつ網羅的に伝えることが求められます。検索意図を考える際は、実際にそのキーワードで検索して上位に表示されているページの構成や内容を参考にするとよいでしょう。
注意点として、自作のSEO対策には限界があることも認識しておく必要があります。たとえば、技術的な修正が必要な場合や、大規模な競合サイトと争う場合には、専門知識やリソースが足りず、思うような効果が出ないこともあります。
また、検索順位にすぐ反映されるとは限らず、成果が出るまでには数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。そのため、短期間で結果を求めず、PDCAを回しながら地道に改善を重ねていく姿勢が大切です。
WordPressサイトであればコードが分からなくてもページタイトルや見出しタグ、画像のalt設定ができますし、コンテンツもブログの更新が自分でできたりするので、外部に依頼せずとも様々な施策ができますが、そうでない場合はHTMLを直接修正したりすることになるので、制作会社に依頼する必要が出てくるでしょう。
SEO対策が意味がないと言われる理由や誤解
SEO対策は「意味がない」と言われることがありますが、その多くは誤解や過度な期待からくるものです。実際には、正しい方法で継続的に取り組むことで成果は着実に出てきます。
「意味がない」と感じてしまう原因の一つは、即効性がないことです。SEOは数日で効果が出るものではなく、通常は数週間から数ヶ月かかります。特に新しいサイトや競合が強いジャンルでは、思うような結果が出るまでに時間がかかるため、「やっても無駄」と思われがちです。
もう一つの要因は、間違った手法で取り組んでいるケースです。例えば、キーワードを過剰に詰め込んだり、機械的に大量のリンクを貼ったりする行為は、かえって検索順位を下げるリスクがあります。過去には多く行われてきたこのような行動は、現在のGoogleのガイドラインに違反しており、検索エンジンからの評価を大きく損ねてしまいます。
また、「SEO対策は一度やれば終わり」という誤解も見られます。しかし実際は、検索エンジンのアルゴリズムが常に更新されているため、過去に有効だった施策が通用しなくなることもあります。競合サイトの動向にも影響されるため、定期的な見直しと改善が不可欠です。
前述の通り、SEOの本質は「検索ユーザーのニーズに応える」ことです。それができていない場合、どれだけ技術的な対策を施しても順位は上がりません。「意味がない」とされる背景には、施策そのものではなく、施策の理解不足や運用の誤りが関係していることが多いです。
SEO対策が本当に効果を発揮するのは、戦略を持ち、ユーザー視点を大切にしたコンテンツ作りを地道に積み重ねていくときです。正しく運用すれば、SEOは非常に価値のあるマーケティング手法となります。
GoogleのアルゴリズムとSEO対策の関係

Googleのアルゴリズムは、検索結果に表示するページを選び、順位を決定するための「ルール」のようなものです。SEO対策は、このアルゴリズムの仕組みを理解し、その評価基準に合わせてサイトを最適化していく作業といえます。
アルゴリズムには数百もの要素が含まれていますが、大きく分けて重要視されているのは「ユーザーの検索意図との一致」「コンテンツの質」「ページの使いやすさ」「信頼性」「被リンクの質」などです。つまり、検索するユーザーにとって価値のあるページであるかどうかが、検索順位に強く影響するということです。
たとえば、あるキーワードで検索したとき、そのページが「役立つ情報をわかりやすく整理して提供しているか」「スマートフォンでも快適に読めるか」「他の信頼できるサイトから紹介されているか」といった視点で総合的に判断されます。この仕組みがあるため、ただキーワードを詰め込むだけのページは現在ではほとんど評価されません。
また、Googleのアルゴリズムは常に進化しており、頻繁にアップデートが行われています。特に大規模なコアアップデートが実施されると、検索順位が大きく変動することもあります。このため、SEO対策は一度行って終わりではなく、定期的に見直していく必要があります。
前述の通り、過去には評価されていた手法が、現在では逆効果になることも珍しくありません。たとえば、以前は「とにかく被リンクを増やせば上位表示できる」という考えがありましたが、現在ではリンクの“質”が重視されるようになりました。不自然なリンクの増加は逆にペナルティ対象となるリスクがあります。
SEOを考えるうえで、Googleのアルゴリズムに対する深い理解は不可欠でが、技術的な話に偏りすぎず、「ユーザーの役に立つサイトを作る」という基本姿勢が最も重要です。
SEO対策の基本戦略と長期的視点
SEO対策を成功させるには、小手先のテクニックだけに頼るのではなく、全体を見通した「戦略」と「継続力」が必要です。検索順位の向上には、正しい方向性と一貫した施策が欠かせません。
まず大切なのは、検索ユーザーのニーズを的確に把握することです。SEOの目的は順位を上げることではなく、「検索経由で質の高いアクセスを得ること」です。そのためには、狙うキーワードに対してどんな意図を持ったユーザーが検索しているのかを調べ、それに合ったコンテンツを用意する必要があります。
次に、サイト全体の構造や導線を整えることも基本戦略のひとつです。ページ同士のつながりを明確にし、重要なコンテンツに適切なリンクを配置することで、検索エンジンがサイト全体を正しく評価しやすくなります。これはいわゆる「内部SEO」に該当しますが、見落とされがちな領域です。
また、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ設計も今後ますます重視されていきます。特に医療・金融・法律などの「YMYL領域(Your Money or Your Life)」では、情報の正確性や発信者の信頼性が検索順位に直結します。誰が、どの立場で情報を出しているのかを明示するだけでも、評価につながるケースがあります。
長期的な視点としては、検索アルゴリズムの変化を前提にした施策設計が必要です。SEOは“数ヶ月で成果が出る”という性質のものではなく、変化するGoogleのルールに柔軟に対応しながら、徐々に信頼を積み重ねていくアプローチが求められます。
流行や一時的なトレンドに振り回されるのではなく、ユーザーの課題解決を主軸に据えたコンテンツと技術の両輪で、安定的に検索流入を増やす。それがSEO対策の本質であり、持続的な成長を目指すうえで欠かせない基本戦略です。
SEO対策に役立つ無料ツールと会社選び
無料で使えるSEO対策ツール一覧

SEO対策には専用のツールを活用することで、効率よく正確な改善が可能になります。無料でも使える優れたツールがいくつもあるため、初心者にも活用しやすいのが魅力です。
まず定番なのが、Google Search Consoleです。これはGoogleが提供する公式ツールで、自サイトの検索パフォーマンスを確認できます。どのキーワードで表示されているか、どのページにクリックが集中しているか、インデックスの状況などを視覚的に把握できるため、現状の課題を見つけやすくなります。
次におすすめしたいのが、Google Analyticsです。ユーザーの訪問経路、ページごとの滞在時間、離脱率などのデータを収集でき、ユーザー行動の可視化に役立ちます。Search Consoleと連携させれば、SEOの効果測定がさらに深く行えるようになります。
キーワードリサーチには、ラッコキーワードという無料ツールが便利です。検索したキーワードに関連する言葉を一括で取得できるため、記事構成やタイトル作成のヒントになります。特に検索意図を探る際に役立つツールです。
さらに、PageSpeed Insightsもチェックしておきたいツールの一つです。ページの読み込み速度を測定し、モバイル・デスクトップ両方のパフォーマンスを改善するための具体的な提案を表示してくれます。表示速度はSEOにも影響するため、対応が必要な要素です。
これらの無料ツールを活用することで、費用をかけずにSEO対策の第一歩を踏み出すことが可能です。ただし、ツールはあくまで分析や補助の役割にすぎないため、得られた情報をどう活かすかが成果を左右します。
データを読み解き、改善に活用する力も同時に育てていくことが成功のポイントですので、そのリソースがない場合は外部のSEO会社への委託も検討することになるでしょう。
SEO対策にかかる費用は月々数万円〜数十万円と様々
SEO対策の月額費用はサービスの内容や契約先によって大きく異なりますが、一般的な相場を知っておくことで予算計画を立てやすくなります。費用の幅は広く、安価なプランで月数万円から、高額なものでは月50万円以上に及ぶ場合もあります。
たとえば、個人向けや小規模サイト向けのSEOサービスでは、月額3万円〜5万円程度のライトプランが用意されていることが多く、キーワード選定や簡単な内部対策が主なサービス内容になります。これらのプランは、コンテンツ作成が含まれていないことが多いため、自分で記事を用意する必要があります。
一方で、中小企業向けのスタンダードなプランでは、10万円〜30万円程度が主流です。この価格帯では、SEO戦略の設計から競合調査、コンテンツの提案・改善、定期的なレポート提出までが含まれることが一般的です。一定の成果を求めるなら、最低でもこのレベルのサービスを検討するのが現実的です。
さらに、競争が激しい業界や全国規模での上位表示を狙う場合、月額50万円以上のハイエンドプランを利用する企業も存在します。この場合、SEOコンサルタントが常駐に近い形で運用をサポートし、細かい改善やABテスト、データ分析なども行います。
なお、SEOには即効性がないため、最低でも6ヶ月以上の継続が必要とされる点に注意が必要です。また、費用の安さだけで業者を選ぶと、短期的な成果だけを狙ったブラックハットSEOを行われ、かえって順位を下げるリスクもあるため、契約内容や実績を慎重に確認しましょう。
最終的に、「何をどこまで任せるか」「どのような成果を期待するか」によって必要な予算は変わってきます。費用対効果を考えたうえで、継続可能な投資計画を立てることがSEO成功の鍵になります。
SEO対策を依頼する会社の選び方

SEO対策を外部の会社に依頼する際は、費用や実績だけでなく、その会社が「何をどこまで対応できるか」をしっかり確認することが重要です。見た目の価格だけに惑わされず、内容と質に目を向けることが成功の鍵になります。
まず見るべきポイントは、実績と具体的な成果事例の有無です。過去にどのような業種・業界の企業をサポートしてきたか、また「検索順位がどれほど改善されたか」「コンバージョンにどんな影響があったか」といった定量的な結果が提示されているかをチェックしましょう。信頼できる会社は、抽象的な説明ではなく、数字や事例を交えて説明してくれることが多いです。
次に注目すべきは、対応範囲と施策内容の明確さです。「SEO対策」と一口に言っても、内部施策・外部施策・コンテンツ制作など多岐にわたります。その中で、自社にとって必要な部分をどれだけカバーできるか、またどのような手法を用いるかを確認することが必要です。特に、前述したブラックハットSEO(Googleのガイドラインに反する手法)を行っていないかは重要な確認項目です。あまりに短期間で成果が出せると謳っているSEO会社には注意した方がいいでしょう。
さらに、レポート提出や運用サポートの有無も見逃せません。月に一度のレポート提出や、施策内容の説明、問い合わせへの対応がしっかり行われているかどうかは、継続的な改善のために不可欠です。不透明な報告しか出さない会社は、施策の中身に自信がない可能性もあります。
見積もりを比較する際は、価格だけでなく「何に対してどれくらいの工数をかけるのか」も確認しましょう。たとえば、月額10万円のプランでも、調査・改善提案・記事制作・レポートまで一貫して対応する場合と、最低限のアドバイスのみを行う場合とでは、費用対効果に大きな差が出ます。
最後に、会社選びで悩んだときは、自社の目的や課題に合った提案をしてくれるかで判断するのが有効です。一方的な売り込みではなく、サイトの現状を丁寧に分析し、適切なステップを提案してくれる会社は、長期的に信頼できるパートナーになる可能性が高いでしょう。
SEO対策の成果を出すための継続的な改善
SEOは一度対策を行えば終わりというものではなく、成果を出すには継続的な改善と見直しが欠かせません。検索エンジンのアルゴリズムやユーザーの検索行動は日々変化しており、固定されたままの施策では競争力を維持できないからです。
まずは、定期的な順位チェックとアクセス解析が基本となります。どのページが検索流入を集めているか、狙ったキーワードで何位に表示されているかを数値で確認し、問題点や改善余地を明確にすることから始めましょう。Google Search ConsoleやGoogle Analyticsを活用すれば、そうした情報を無料で把握できます。
改善の第一歩は、コンテンツの更新です。古くなった情報を修正したり、見出し構成を整理し直したりするだけでも、検索順位が改善されるケースは少なくありません。特に競合サイトが新しい情報を出している場合、自社ページが取り残されてしまうリスクがあります。
また、ユーザー行動の分析をもとにした改善も重要です。直帰率が高いページや滞在時間が短いページは、読みづらさや情報不足のサインです。本文の構成を見直したり、図解や箇条書きを使ったりすることで、ユーザー体験を高めることができます。
さらに、新たなキーワードの追加や派生ページの作成も継続的な対策に含まれます。たとえば、「SEO 対策 費用」というキーワードで上位表示されているページがあるなら、「SEO 費用 相場」「SEO 料金体系」といった関連語にも対応した記事を増やすことで、サイト全体の評価が底上げされる可能性があります。
継続的な改善には手間と時間がかかりますが、それによって得られる「検索流入の安定化」は長期的に見て非常に大きな価値を持ちます。一時的なテクニックに頼るより、着実な見直しとブラッシュアップを重ねていく姿勢が、SEO対策で成果を出すもっとも効果的な道といえるでしょう。
SEO対策の全体像と取り組みのポイント
最後にSEOについてまとめます。
- SEOとは検索エンジン最適化を意味し、上位表示を目指す施策全般を指す
- 内部対策・外部対策・コンテンツ対策の3つが基本となる
- 内部対策ではHTMLタグやサイト構造の最適化が重要
- 外部対策では自然で信頼性の高い被リンク獲得がカギとなる
- コンテンツ対策は検索意図に応える質の高い記事作成が中心
- SEOは一度の施策で完結せず、継続的な見直しが必要
- 自分でSEOを行うにはGoogleのガイドライン理解が不可欠
- ユーザー目線のコンテンツ作りが最も重視される
- SEOには即効性がなく、成果までに時間がかかる
- 間違った施策は逆効果になり順位が下がることもある
- 無料ツールを活用すれば効果的にSEO分析ができる
- SEO専門会社に依頼する場合、月額費用は数万円から数十万円まで幅があり目的で選ぶべき
- 会社選びでは実績・対応範囲・報告体制の確認が必要
- Googleのアルゴリズムは進化し続けるため常に最新の対応が求められる
- 成果を出すにはデータをもとに地道な改善を繰り返すことが重要
皆さんのWebサイト運営に役立てていただけると幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました!